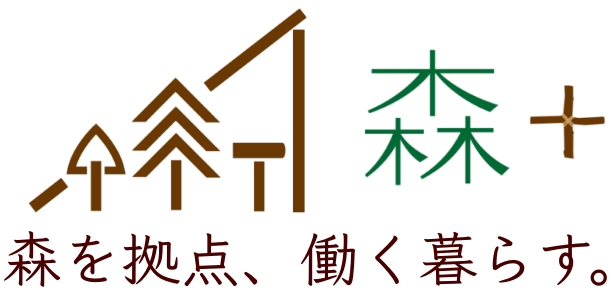森とやりたいこと、好きなことを足し算して、可能性を広げ、新しいコトやモノを生み出していく。それが「森プラス」です。
ゼロから森を開拓する、小さな家をつくる、森の恵み、森の循環、そして森を育てる・・・。
素の自分に戻る、リセットできる場所をつくる・・・。
人生を自分の手で切り拓いている実感を得る・・・。
森プラスをはじめるに至るまでには、これまでさまざまなプロセスと出来事がありました。
ここでは僕たちが現在に至るまでの経緯を記します。お時間があるときにでも読んでいただけたらうれしいです。
働き方生き方をサポートする

働き方、生き方にモヤモヤを抱える人たちが自分の足で立つ術を身につけ、いきいきワクワク元気に毎日を送ってもらう。
すったもんだサラリーマンを23年やって独立、その後現在まで15年に渡ってやり続けてきた生業です。
そうした人たちに共通して必要なのは、「自分の心に素直になること」「素直な気持ちでシンプルに考えること」でした。
一見簡単そうに見えて、実は現代社会では最も難しい話です。じゃあ、どうしたらそうなれるのか。あらゆる視点でアプローチしてきました。
試行錯誤を重ね、柱になったのが焚き火の場づくりでした。
焚き火でフラットな場をつくる

学生時代に経験した焚き火の場。火を囲むと言わなくてもいいことまで話してしまう、そのままの自分が出せる心地良い空気感・・・そうだ、焚き火をしよう。思い立ちました。
それから10年強の間、焚き火コミュニケーションの場をつくる活動をやってきました。最初はキャンプ場を使いながらそれなりに成果を得てきました。
でも借りた場所では自分が思ったようにはなりません。制約があるとやりたいことができない。行き詰まりを感じます。
もっと自由に焚き火がらできる場所を求め、動き始めます。
2018年、埼玉ときがわ町の山手に100坪ほどのログハウスを見つけます。
ここをプライベートで焚き火がたのしめる場にしました。同時にこじんまりと宿の運営もスタートさせます。
それから4年間、おかげさまで多くの方にご愛顧いただくまでになりました。
「ここでは物足らない。もっと広いフィールド、木々の美しい場所。本当にやりたいことはここではない。チャレンジしよう」
その間にくすぶっている気持ちです。そしてまた新たな土地を探し始めます。
新しいことを始めるにはけじめが必要、2021年末をもって焚き火の宿に終止符を打ちました。
それなりの広さ、美しい木々、清々しさ。何より自由に自分の手でゼロから開拓できること。いくつかの条件であちこち歩き回ります。
北海道から始まり、山梨、長野へと約1年半。
2022年3月、行き着いた先。信州小諸のフィールドに出会いました。
拠点づくりがスタートします。森を開拓、小さな家をつくる。
暮らしづくりが始まります。
この地へ来て、これまでやってきた「働き方軸」から「暮らし方軸」へと視点が広がりました。
暮らし方から生き方をつくっていく立ち位置です。
仕事場ありきで二拠点生活をする
「都会を離れて田舎暮らしがしたい」「リフレッシュできる場所がほしい」「日常を離れ、静かに暮らしてみたい」「豊かな自然に触れ合いたい」・・・
二拠点生活をやってみたい人が思うことですね。
僕たちの場合はちょっと違います。僕たちが二拠点生活になった理由は、二拠点生活がしたくて始めたのではなく、先に仕事場ありきで、やり始めた結果、二拠点になったという流れです。
焚き火の場づくりとして、自分が思ったように自由にできる場所を探した。すると山の中のログハウスに至った。週末に宿やイベントをやるようになったので通い始めた・・・そんな感じです。
その後、さらに広くて木々が美しいフィールドを求め、信州小諸の地と出会いました。森の開拓、小さな家を町と往復しながら進めてきました。どれも仕事場です。
働く場所を固定化しないこと。自分が最も力を発揮できる環境に身を置くのがベストであること。
まさに今、腑に落ちています。
世の中で今まで当たり前と思っていたことを全てリセット。
シンプルに物事を考え、自分が生きていくためにベターと思えることを実行に移す。答えのない今の時代に必要なことと感じます。
こうした感覚、ライフスタイルに共感してもらえる一人でも多く人に伝えていきたいと思うようになりました。
働く場所を固定せず、自分にとって心地良い環境で、新しいシゴトをつくりだす出す。
僕たちがもつ重要なテーマです。
森+開拓

誰にも気兼ねせず、自由に静かに焚き火ができる場所をつくっていきたい。もっと広いフィールドで可能性を広げていきたい。当初はその想いで土地を探し始めました。
焚き火は木から生まれます。落ちた木枝、割った木から薪ができます。焚き火の先には森の存在があります。こだわったのは木々の美しさでした。
1年半探し続けて、やっと見つけたこの地。何もない倒木だらけの荒れた森林の開拓がスタートしました。
開拓といってもずぶの素人、当時58歳と56歳の夫婦ふたりの手づくり作業。木をどんどん伐り倒したり、重機を入れてガシガシやるような開発行為とは真逆の世界。
その時その時、森として考えられることを考える。自分たちのペースでできることを。天候にも左右されながら少しずつ進めてきました。
こうした毎日を送る中、感じるようになったのは「開拓作業そのもののたのしさ」。


道を広げるためにスコップで土を掘る、次々に出てくる根を一つひとつ切る、草を刈る、土を運ぶ。
倒木を伐採する、丸太を運ぶ、玉切りにする、木枝を拾って薪にする、穴を掘る、落ち葉を集めて腐葉土をつくる、杭を立てる・・・

一つひとつの作業は単純、何一つややこしいことはありません。その分、ひたすら目の前のことに一生懸命に向き合わないと前に進みません。
没頭、集中、頭の中は真っ白。
作業をしているときはそのことだけしか頭にありません。作業を終えると身体は目一杯疲れます。
でもその疲れが何とも心地がいい。都会で感じるいやな疲れはかけらもありません。

日が昇って日が沈むまで全力で作業に取り組む。その日その日で物事は完結。そして明日はこうやろう!と活力が湧いてくる。


林業、土木業、造園業、建築業、農業・・・森の開拓をしていると、さまざまな領域に顔を突っ込みます。
今まで経験したことのない「人生初」の連続。新鮮さと刺激の毎日。学ぶ意欲がかき立てられます。

ゼロから自分が思い描いた絵を自分が思うように切り拓いていく。やっていく中で苦難にぶち当たる。
ぶち当たったつど、工夫する。アイデアを出す。乗り切る。そしてまたやりたい絵を描き続ける。
ある意味、森の開拓は自分の人生づくりと似ています。
開拓でしか味わうことができないこの感覚を分かち合いたい。そしてご縁のあった人を元気にしたい。いつしか自然にそんな想いにかられるようになりました。
「森+開拓」は、こうしたプロセスから始まっています。
森+小さな家づくり

最初、焚き火のフィールドをつくろうと考えた頃は、「2~3日滞在できる小屋でもつくろう」という感じでした。
開拓作業をしながら、地に足ついた活動をするには現地に根を下ろさないといけない。二拠点ではなく移住だ!考え方がシフトしていきました。
たまたま同じタイミングで信州小諸の近隣に住む知り合いの一級建築士とのご縁もありました。ここで商いを始めるなら事務所兼用もありだろう。
「よし!ちゃんと住める家をつくろう」そんな想いにかられました。「どうせやるなら自分の力でできるところまでやってみたい」
日本古来の軸組み工法にチャレンジする。いつもの無謀な好奇心が湧いてきます。

こうして土を掘り起こして基礎をつくるところからスタートしたのが2022年10月。その後、土台、柱、桁、梁、そして屋根、壁と段階を進み、外形をつくる。
そして石膏ボード、漆喰、根太、フローリング、玄関、キッチン、洗面台。内装へと進んでいきました。
小さいながらもきちんと家をつくることはそれ相応の取り組みになりました。
それこそわからないことの連続。どうなるかが先が見えない手探り状態。
何度も「もうだめかも」という場面を繰り返し、失敗を重ねながら一つひとつ丹念に積み上げてきました。

建築という今まで全く接点のなかった世界、まさに毎日が「人生初」の連続です。
そしてその出来事一つひとつが人生に置き換えできる意味深いものでした。そしてこれからもきっとそうなることは間違いありません。
こんな体験を自分たちだけに留めていくのはあまりにもったいない。
「森+小さな家づくり」。自分たちがやってきた足跡を整理し、こんな暮らし方、生き方に関心をもつ人へ伝えていきたいと考えています。

森+店舗アトリエ

森を拠点に暮らしていくには「仕事」が必要です。リモートワークを駆使すれば場所を選ばず仕事はまわせます。
信州小諸へ至るまでの二拠点4年間とここでの3年間での実践から確証を得ていました。
一方でもう一つ、新たな事業を立ち上げていく必要がありました。不動産業です。森の暮らしをサポートしていくには物件紹介なしでは語れません。
2024年2月宅建士資格取得後、宅建業免許を得るため、事務所をつくることに。紆余曲折を経て2024年12月に完成。
「森で自分がやりたい好きなことでお店を営んでもらうのもいいね!」
店づくりの経験と起業複業支援をしてきた知見で、森の中で小さなお店やアトリエを開業するサポートをしていくメニューをオンしました。
森+育てる

フィールド内に数十年自生するアカマツ。来た当初からできるだけ木は伐らないで進めていきたいと考えていました。でも実際に現場に入るとそんなきれいごとだけでは進みません。
枯れた木はいつ倒れてくるかわかりません。風雨にさらされると危険度は上がります。
ある日の朝フィールドに到着すると、大木が二本倒れて、そのうち一本がテントを直撃し粉々になっていた光景を目の当たりにしたこともあります。
木が生い茂ると光が入らなくなり、下草も生えずひょろひょろのものが増えていきます。
適度に間引き(間伐)しないと森は育っていきません。森の手入れという言葉を知ったのがこの時でした。

「危ないから倒さないといけない」赤松は、地元の人にもどちらかというと厄介者扱いされています。
危険性から言えばその通りです。でもそんな赤松にも良いところがあります。

倒れて腐った赤松の枝の根本からは、ファットウッドという自然の着火剤が採れます。
冬の低温下でなかなか火が着きにくい環境でもファットウッドを削ればすぐに着火。とても優れもの、しかも天然物です。

秋になると地面を覆うほどになる落ち葉。雨や雪にさらされ、微生物が長い時間をかけて分解することで、やがて土の肥やしになる。まさに自然の腐葉土です。
粘土質の土壌にはこの自然の腐葉土が大切な役割をしています。

森にいると空気のおいしさを実感します。まさに澄んだ空気です。
木々は育つ過程で空気中の二酸化炭素を吸い込み、きれいな酸素を吐き出します。そんな理科の時間の話を思い出します。
これらはほんの一つの例でしかありません。森の中にはまだまだ知らないことが満載、いろいろな事象があります。
まさに森の恵みひいては森の循環。
「森+育てる」。まだまだ勉強することが山ほどあります。でも育てるという行為がどれだけ大切なことかの一端を感じるようになりました。
別荘地とのご縁

山林を探し求めるとなぜか出てくる物件の中に混在するのが別荘地。「別荘地?管理された場所なんて面白くないし使えないよな」最初はそう思っていました。
そうした中、別荘地物件を一つひとつをみていきます。すると多少荒れてはいるものの、木々の感じがきれい、周囲の環境が良さそう・・・選択肢に加えてみようかと思うようになります。
僕たちは1000坪を超える広さが欲しかったので、別荘地そのものを選ぶには至りませんでした。ただご縁があって別荘地に隣接した土地を手に入れました。そのことでより客観的に別荘地を知ることができるようになりました。
別荘地というとリッチな人たちが住むイメージがありますよね?でもそれはひと昔、土地神話など言われた時代の話です。その頃に買い求めた物件がそのまま放置状態になっていて物件探しにヒットするわけです。
土地の持ち主は子供たちに引き継げるわけでもなく、少しでも早く処分したいという物件も多々あります。宙に浮いた状態になっているわけです。
こうした背景もあり、道路に倒木がそのままになっていたり、草木がそのまま伸びて荒れた土地になったり、ゴースト化している別荘地も少なくありません。
一方で別荘地というだけあって、景観は良く樹木は美しいものが多い。少し手を入れ整備したら見違えるようになる森林もたくさんあります。そんじょそこらの山林とは種類が違います。
自分たちの開拓フィールドを別荘地隣接の地に定めたことから、こうした現実を目の当たりしてきました。「もったいない。何とかならないものか・・・」想いは募っていきました。
そして開拓活動を始めると、別荘地に住む人たちとも接点をもつようになりました。多くは80代前後の人生の大先輩ばかり。
20数年前まで都市で生活、その後二拠点生活を経て森の別荘地へ移住してきた先駆者。
大手ゼネコンを辞し家具職人となったり、広大な敷地を自らの手で開拓しつつガーデンづくりをしたり、移築した古民家で地元で評判の蕎麦屋さんを営んだり・・・
年齢を感じさせない生き生きとした姿に、閉塞感のあるこれからの高齢者社会のロールモデル像を描いています。
「頑張ってね」「期待してるよ」と散歩の途中でお声がけをいただく。農家さんでもらったものをお裾分けいただく。こうして気にかけていただける人たちの何かお役に立つことはできないだろうかと考えるようになりました。
「美しい自然をもっと生かしたい」「活用アプローチを変えたらもっと有効利用できる」「とにかく放置されているのはもったいない」「居住者がたのしく元気になることがしたい」
別荘地活性化活動はこんなところから始まっています。